Install Steam
login
|
language
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem

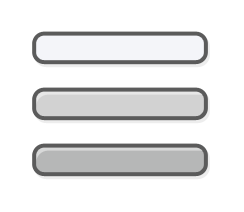




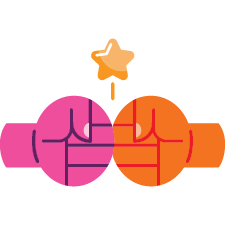
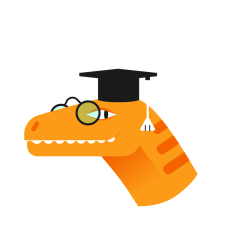




![scope_out_2.gif] scope_out_2.gif]](https://images.steamusercontent.com/ugc/1002520959937435921/2813493020CCF3DDFA36E9128DE1A86B36C46242/)























走って近づき、威嚇されたら近くの岩場や木に隠れてルアー。大事だと分かりました。
情報いただきありがとうございます。確認してみます。
他にもいろいろ修正が必要な個所がありそうです
Fixed binoculars and other optics to use Aim Sensitivity instead of Look Sensitivity
双眼鏡やその他の光学系で、ルック感度ではなくエイム感度を使用するように修正しました
ガイド作成ありがとうございます!